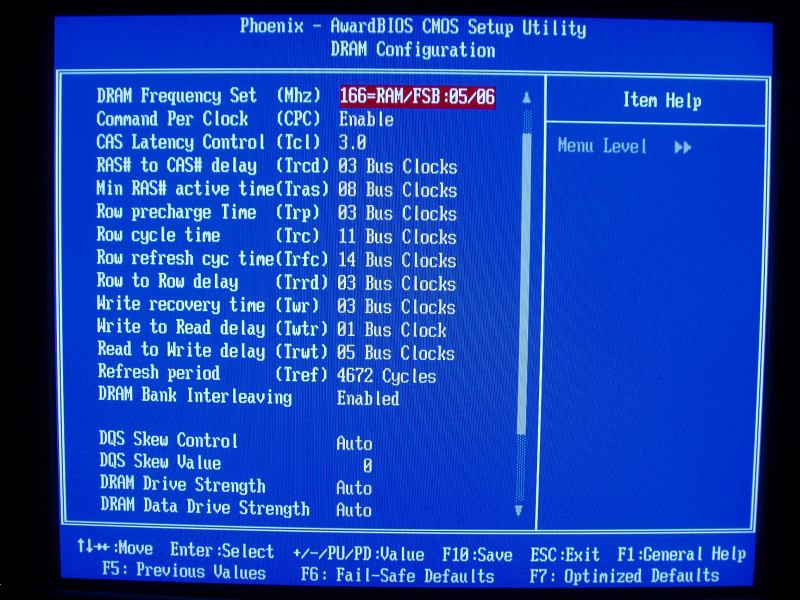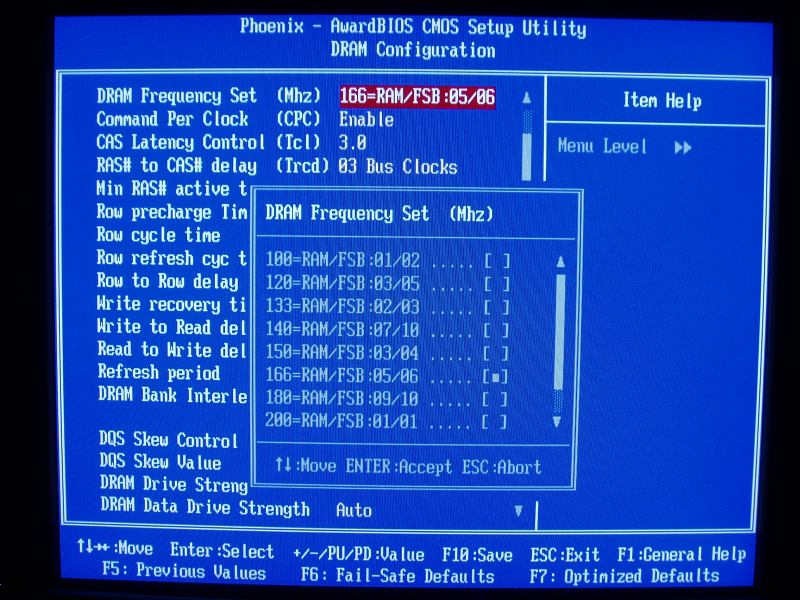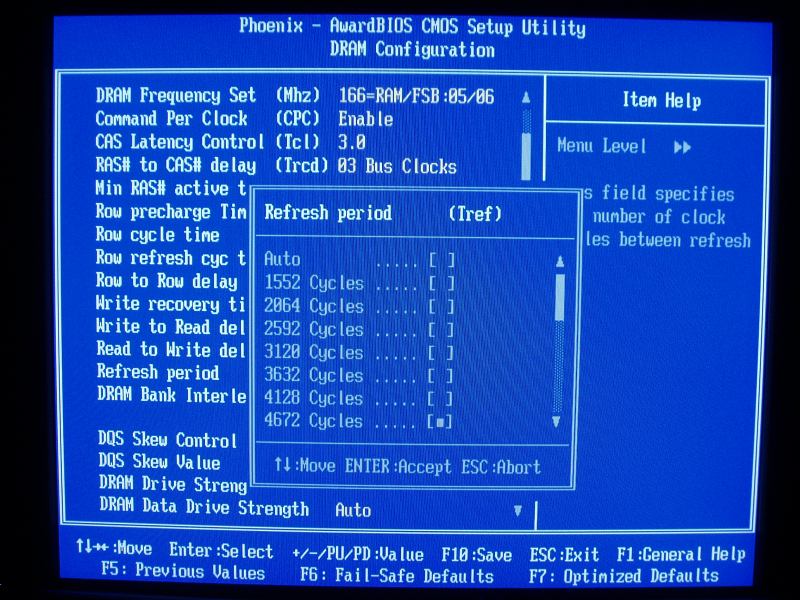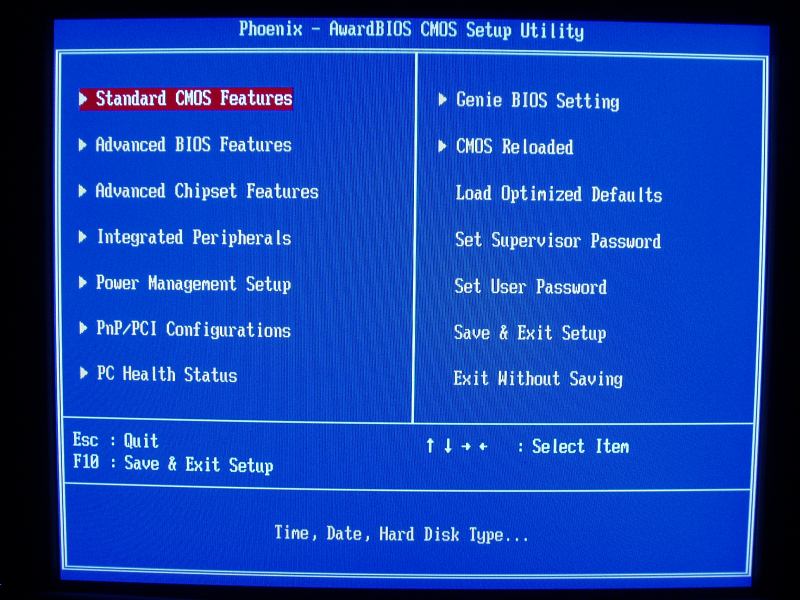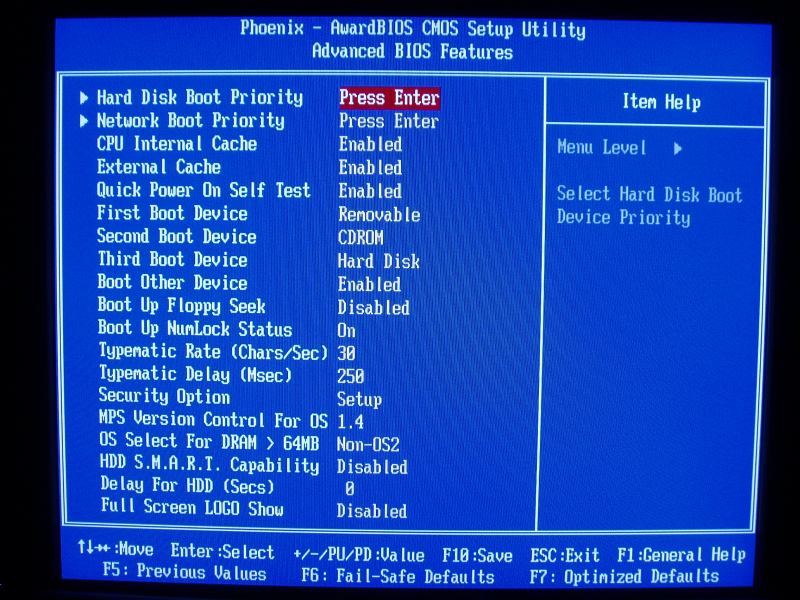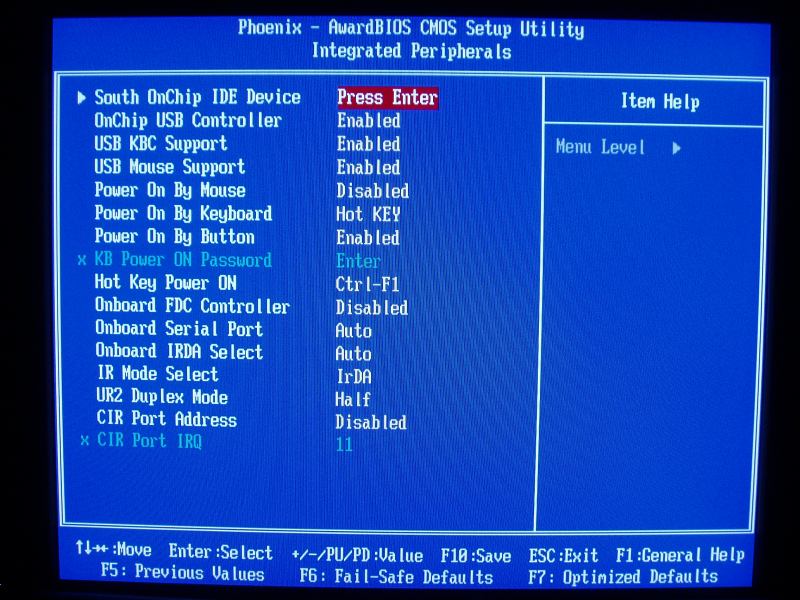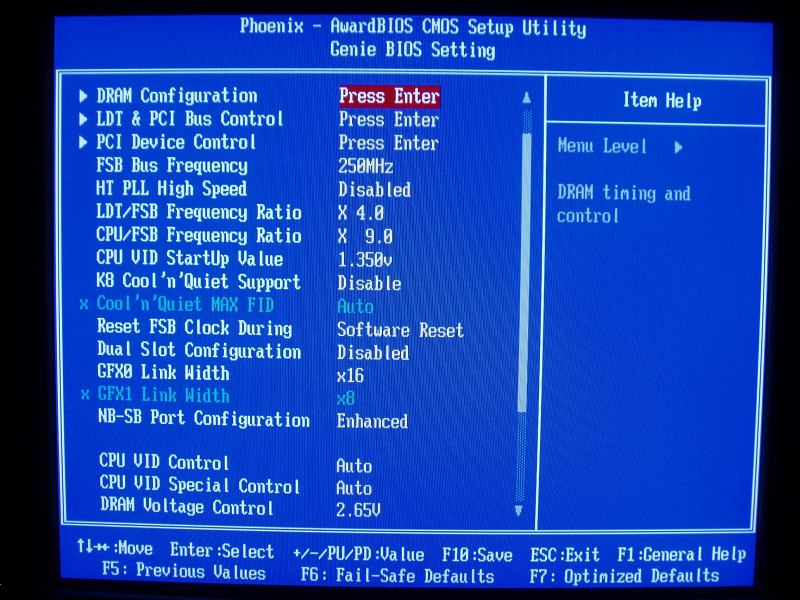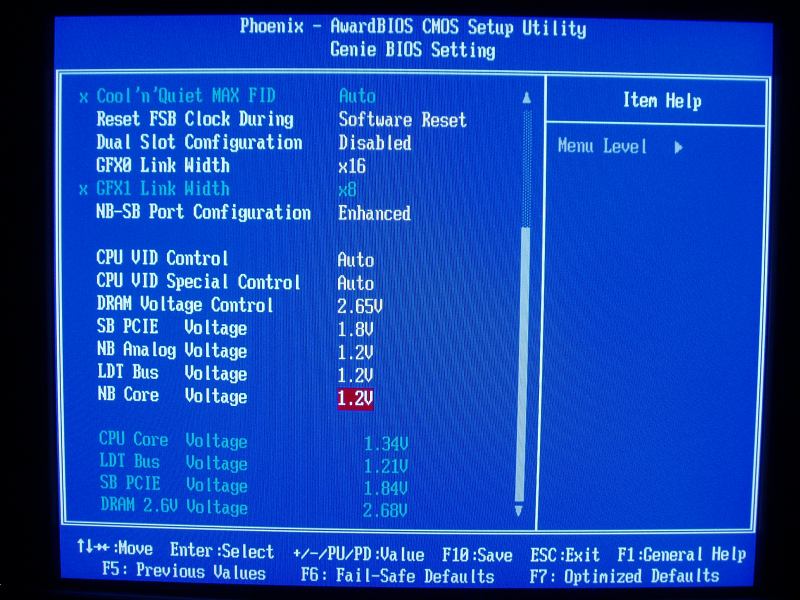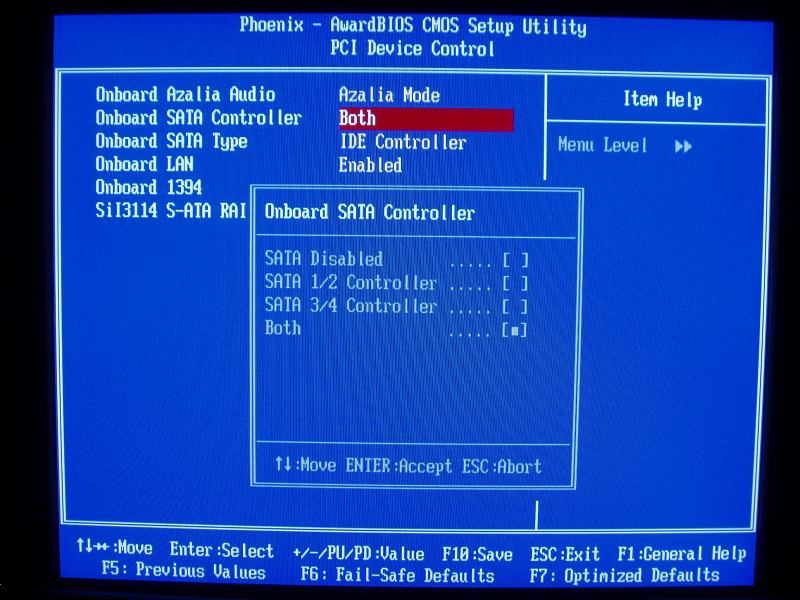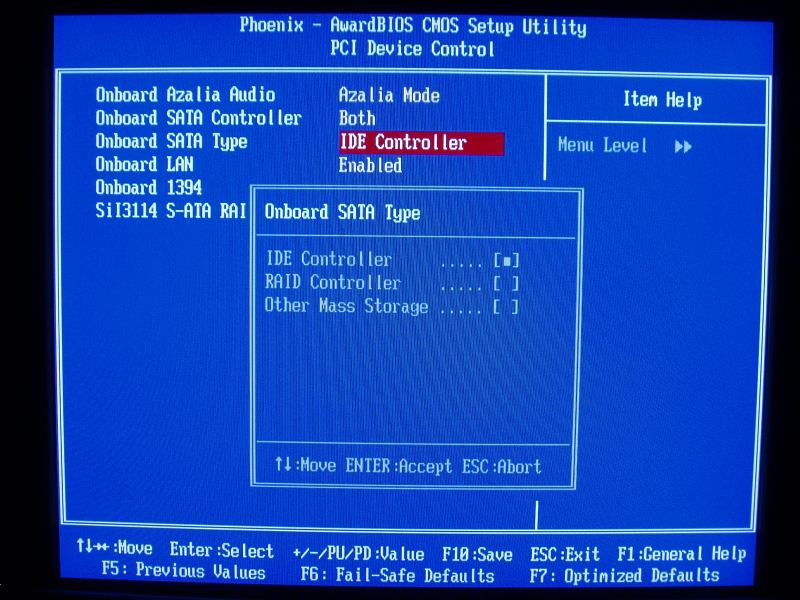|
レースゲーム関連、PC関連、Game関連等の話題フリーな掲示板 特に制限はありませんので、気軽に書き込んでいってくださいな(^−^) |
|
32 / 175 ツリー | ←次へ | 前へ→ |
| 【684】DFI 「LANPARTY UT RDX200 CF-DR」 IR@管理人 06/10/2(月) 21:40 |
| 【685】メモリ関連 IR@管理人 06/10/2(月) 21:43 |
| 【687】メモリ関連の写真 IR@管理人 06/10/3(火) 23:00 |
| 【693】メモリ近辺の冷却方法 IR@管理人 06/10/13(金) 21:37 |
| 【686】BIOSとか IR@管理人 06/10/2(月) 22:02 |
| 【688】BIOS関連の写真 其の一 IR@管理人 06/10/3(火) 23:04 |
| 【689】BIOS関連の写真 其の二 IR@管理人 06/10/3(火) 23:04 |
| 【690】再起動病デター・・・・orz IR@管理人 06/10/4(水) 20:20 |
| 【694】現時点でのまとめ IR@管理人 06/10/13(金) 21:48 |
|
IR@管理人 - 06/10/2(月) 21:40 - |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/2(月) 21:43 - |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/2(月) 22:02 - |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:00 - |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:04 - |
|
|
||
|
||
|
IR@管理人 - 06/10/3(火) 23:04 - |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/4(水) 20:20 - |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/13(金) 21:37 - |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IR@管理人 - 06/10/13(金) 21:48 - |
|
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
32 / 175 ツリー | ←次へ | 前へ→ | ||||
|
4,687 | |||||
|
(SS)C-BOARD v3.8 is Free |
||||||